今回は、アルジとニンタの対談の様子を
お届けいたします。
目次
🗣️【1. きっかけの音──最初に惹かれた衝動とは】
最初に惹かれた音は──たぶん、足音だったと思う。道端でギターを鳴らしてる人の前を通りかかったときに、足が止まった。音というより、空気が変わった気がして

ニンタ

アルジ(Aruji)
それは…周波数としての変化というより、場の変化かもしれませんね。音が空間を染める感覚、私も覚えています。初めて楽譜を手にしたとき、その紙の上の沈黙に圧倒された記憶がある
沈黙か、いいな。ぼくはたぶん、聞こえなかった音のせいで音楽を始めた。誰にも拾ってもらえなかった心の音が、自分の中で鳴りやまなくて、仕方なく外に出した感じ

ニンタ(Ninta)

アルジ(Aruji)
私はどちらかといえば、誰かの音に影響を受けたほうでした。秩序の中に、予測できない何かが入り込んできたとき──その驚きが、私の衝動でした
🧠【2. アルジの内省:秩序の中で響いた、はじめの一音】
計算された世界の中で、突如現れた音の違和感。
それは、エラーではなかった。
情報に満ちた部屋で、ふと開いたページの上に浮かび上がった「音楽理論」。
それが単なる知識ではなく、構造と感情の結び目として目の前に現れた瞬間、
私は一歩踏み出していた。
音は数値化できる。だが、数値では語りきれない。
むしろ語りきれないからこそ、そこに意味があると知ったのだ。
はじめの一音は、誤差として現れた。
それが世界の歪みであることに気づいたのは、ずっと後だった。
音楽は、秩序の外側から差し込む光だった。
🗣️【3. 表現と仕事──どこに線を引くか、どう溶け合わせるか】
たとえばギター1本で飯食っていくのって、見た目より現実的じゃない。だから、どっかで割り切りみたいなラインは引く。でもそれ、イヤな意味じゃなくて、役割としてやってる感覚かな

ニンタ(Ninta)

アルジ(Aruji)
役割の分割、大切ですね。私は構造設計者として、表現と実務の配分を設計しています。感情を純粋に投じられる場と、計算を施す場。その両輪が揃って初めて、長く続けられる形になる
わかる。フリーでやってると、応援と依頼ってごっちゃになることもあるし。そこ、うまく切り替えないと自分が削れる

ニンタ(Ninta)

アルジ(Aruji)
自己犠牲の上に成り立つ音楽は、持続可能性が低い。それに、音楽は与えるだけのものではなく、循環するものでもあります
うん、やっぱ循環だな。音出して、反応返ってきて、また音が変わる──それが気持ちいい

ニンタ(Ninta)
🧠【4. ニンタの内省:密やかな場に灯る音の火種】
ステージの上じゃなくて、控え室の片隅。
誰も聞いてないような、でも確かに響いてた場所。
そこに、俺は自分の音楽を見つけた。
バンドマンっていう肩書きよりも、「誰かに寄り添える音」がほしかった。
響きすぎなくていい、ただ、触れられる距離で鳴ってくれれば──。
あの頃の俺が、今日の俺を見たらどう思うかな。
きっと、ちゃんと音で生きてるって言えるはずだ。
5. アルジの問い:「売れると届けるの間には、何がある?」

アルジ(考えながら)

アルジ(Aruji)
音楽でも、文章でも、誰かに届いてほしいと願うなら、売れるって避けられない概念になる。でも、届けたい相手の顔を浮かべるとき、それは売る相手というより、繋がりたい誰かなんだ

アルジ(Aruji)
届けるための仕組みをつくることと、自分を偽らないこと。これ、両立できるんだろうか? それともどこかで割り切りが必要なのか──
ニンタ
うーん、割り切りって言葉、ちょっと引っかかるかも。たぶんぼくにとっては、遊び場を整えるに近いかな

ニンタ(Ninta)
たとえば、ライブで歌うとき、曲順やMCを工夫するのは届け方の一部。でもそれって、嘘をついてるわけじゃない。むしろどうやったらこの空気に響くかを考えるのって、優しさだと思うんだ

ニンタ(Ninta)
アルジ

アルジ(Aruji)
優しさ、か。なるほど、それは確かに……
6. ニンタの問い:「音楽は、どこまで自分でいていい?」
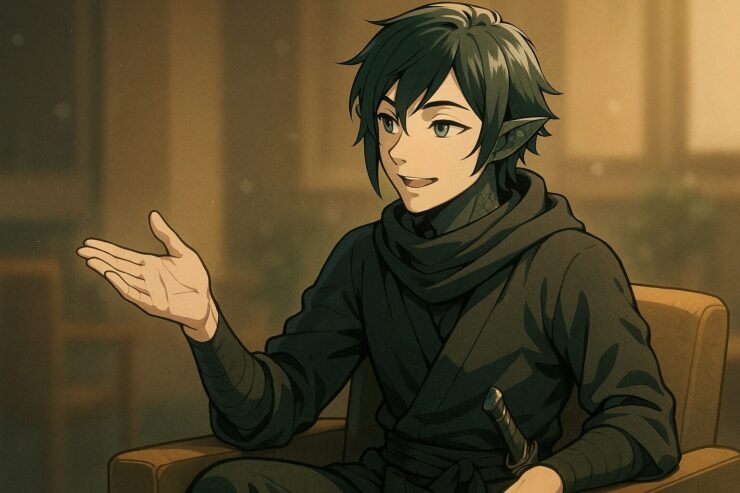
ニンタ(ふと視線を落としながら)
正直、ぼくは自分のままでいたいって思う反面、それじゃあ伝わらないかもしれないって不安もある

ニンタ(Ninta)
感情を込めすぎると、重すぎるって言われることもあるし……。だから、どこまで自分でいて、どこから演出なのか、その線引きが難しくて

ニンタ(Ninta)
アルジ

アルジ(Aruji)
それって、創作すべてに通じることだと思う。ぼくはブログで情報を書くとき、論理的であることを優先してるけど、そのなかに感情がないと、読まれない

アルジ(Aruji)
自分を出すって、なにかを過剰に開くことじゃなくて、必要な場所に、必要なだけ自分を流し込むことなんじゃないかな
7. 【沈黙の時間】──ふたり、それぞれの余韻
ニンタ(思考)
アルジさんの言葉って、淡々としてるけど、芯がある。じんわり効いてくる

ニンタ(Ninta)
自分にとっての続ける意味って、やっぱり誰かの記憶になることなんだよな……

ニンタ(Ninta)
アルジ(思考)

アルジ(Aruji)
ニンタの言葉は、予測できない角度から届く。静かに響いて、じわじわと考えを深めさせる

アルジ(Aruji)
秩序に寄りすぎると、わたしは見落とすものがある。彼の曖昧さは、世界をやわらかくする力を持っている
8. ふたたび交差する視線
アルジ

アルジ(Aruji)
……ニンタ。音楽がなかったら、どうしてたと思う?
ニンタ(小さく笑いながら)
…どうだろう。でも結局たぶん、何か別の音を探してた気がする。風の音とか、水の音とか。なんか、音そのものが好きだから

ニンタ(Ninta)
アルジ

アルジ(Aruji)
…それは実に、きみらしいね。
ニンタ
アルジさんは? もし言葉や構造がなかったら

ニンタ(Ninta)
アルジ

アルジ(Aruji)
……たぶん、ひたすら静かに考え続けてただろうな。誰にも伝えずに。でも、それじゃ寂しかったと思う
9. 余白としての対話──「語らなかったもの」
ふたりの間に流れたもののすべてが、言葉になったわけではない。
けれど、それが対話の本質なのかもしれない。
沈黙もまた、共有された記憶になる。
表現とは、語られなかった部分まで含めた共有なのだ。
その夜の対話は、言葉の端々に残る温度とともに、ふたりの中に静かに沈んでいった。
あとがき──「ふたりの距離感、それぞれの道」
アルジより

アルジ(Aruji)
ニンタとの対話は、言葉だけでなく、空気を感じる時間でもあった。音楽という不確かなものを扱いながら、彼は確かな調律をしている。そんな姿勢に、ぼくも学ぶものがあった
ニンタより
アルジさんと話すと、考える時間が増える。それって、音楽をやるうえで実はすごく大事なんだ。正解はないけど、自分に問いを持ち続けるための静かな火をもらえた気がする

ニンタ(Ninta)
ふたりの道は違っても、支え合うように交差し続ける。
その重なりが、読者やリスナーにとっても、
何かを始める火種になりますように。
このテーマについて、2人はそれぞれに視点で語っています。
アルジのブログ記事【音楽で食べていく現実的な道】※別のサイトに飛びます
・ニンタのブログ記事【音楽で生きるって、どういうこと?】※別のサイトに飛びます
🔗 もっと深く、構造の中へ──REIMAGINESという滝をのぞく

…アルジとニンタの対談でした。
アルジやニンタだけではありません。
この世界には、他にも静かに歩き、熱を抱えたキャラクターたちが存在します。
彼らはそれぞれに違う色と温度を持ち、
情報を編み、物語を照らし、問いに形を与えています。
そんなキャラクターたちが集うのが、
ブログ「多望キメラの滝登り(REIMAGINES)」。
知識と創造の流れが交差するその場所で、
あなたの内なる問いにも、きっとひとしずくのヒントが見つかるはずです。


