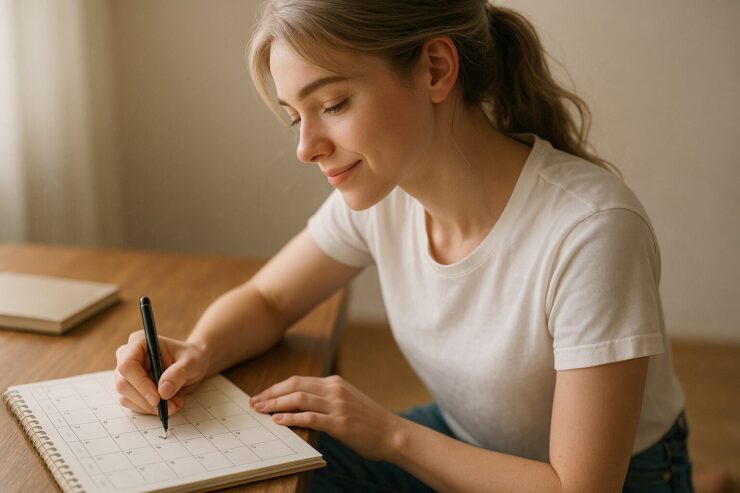「また続かなかった」「どうしても3日目で止まってしまう」
そんな言葉を、自分に何度も投げかけてきた人へ。
継続ができないのは、あなたの意志の弱さではありません。
問題は、「どう続けるか」ではなく、「どう積み上げるか」の設計にあります。
本記事では、「積み木式継続」という思考法を紹介します。
モチベーションが上下しても続けられる、小さな成功の積み重ね方。
ルーティンや習慣形成に苦手意識がある人でも、自然と続ける人に変わっていける方法を、構造的にひもといていきます。
目次
3日坊主は続かないのではなく計画がズレてる
「どうせ私には続けられない」「また三日坊主だった」
そんな風に自分を責めた経験がある人は少なくないはずです。
けれど本当に問題なのは、あなたの意志の強さではありません。
継続できなかったのは、あなたに合っていない設計をしてしまったからなのです。
たとえば、朝が弱い人が「毎朝5時に起きて走る」という目標を立てたとします。
初日は気合いで起きられるかもしれません。でも、2日目・3日目になると、「疲れ」や「習慣の摩擦」が出てきます。
そして「できなかった自分」だけが記憶に残り、「やっぱり私には無理なんだ」とあきらめてしまうのです。
ここで大切なのは、「できなかった自分を責める」のではなく、
ズレた設計を見直す視点を持つこと。
習慣とは、自分の生活リズム・性格・環境に寄り添ったときに初めて定着します。
つまり、「続かない人」なのではなく、「続けられる形にまだ出会えていない人」というだけなのです。
「積み木式継続法」とは何か
「積み木式継続法」とは、
完璧な目標を立てるのではなく、小さな手順を1つずつ積み上げていく方法です。
よくある失敗のパターンは、「いきなり完成形を目指してしまうこと」。
たとえば「毎日1時間勉強する」「筋トレを週5でやる」など、理想としては素晴らしいけれど、
現在の自分の生活やリズムにフィットしていない目標を設定してしまうことが多いのです。
そこで「積み木式継続法」では、最初から高いハードルを飛ぼうとせず、
まずできる最小単位からスタートすることを前提にします。
たとえば──
- 「机に向かうだけでOK」
- 「アプリを開いたら達成」
- 「1ページ読んだら終わっていい」
このように始めやすさに全振りすることで、行動のハードルを極限まで下げるのです。
それを、まるで積み木のように、少しずつ、確実に積み上げていく。
最初は「物足りない」くらいでいい。
むしろもっとやりたいと思ったタイミングで終えることが、
「継続したい」という欲を次の日につなぐ鍵にもなります。
大事なのは、「今日はできた」という成功体験を重ねていくこと。
それこそが、自己肯定感と習慣の両方を育てる、積み木式の本質です。
【設計術】目標より手順を積む
私たちはつい、「◯◯できるようになる」「△△を達成する」といった目標にばかり意識を向けてしまいがちです。
しかし本当に大切なのは、その目標にどうやって辿り着くかという道のりの方です。
目標と手順は、別の設計図
たとえば「1ヶ月で5kg痩せる」という目標。
その目標を立てただけでは、具体的に何をすればいいのかが不明確です。
ここで「積み木式継続」の発想を持ち込むと
「毎日1駅分だけ歩く」「夜9時以降は水以外を口にしない」といった、
今日から実行できる、具体的な一歩に分解していくことができます。
つまり、結果ではなく行動レベルにまで目線を下ろす。
これが、積み木式の設計術です。
頑張ればできるは続かない
気合いや根性に頼った継続は、環境や気分にすぐ影響されてしまいます。
でも「手順として組まれている行動」は、考えずに行動できるという強みがあります。
たとえば──
- 朝起きたら白湯を飲む
- アプリを開いたら3分だけタイマーをセットして読書
- ノートの左上に日付だけ書く
このように小さな行動が仕組みとしてセットされていると、脳はスムーズに動き出します。
やる気は後からついてくる。
大事なのは「行動の型」が先にあることです。
1日でも空いたら…仕切り直しの構文を持つ
どんなに丁寧に設計した習慣でも
人間ですから、必ず「できない日」が訪れます。
体調が悪かったり、予定が詰まっていたり、気分が乗らなかったり。
そんな日は、積み上げた習慣が崩れたように見える瞬間が訪れます。
そして多くの人が、こう考えてしまうのです。
「せっかく続いてたのに、台無しだ」
「一度サボったら、もう終わりだ」
その結果、積み木を全部崩すように、継続を諦めてしまう。
でも、本当にそうでしょうか?
「仕切り直し」は失敗ではなく設計の一部
積み木式継続法の本質は、「続けること」ではなく、
やり直せる構文を持つことにあります。
1日空いたら、次の日にこう書きましょう。
- 「ここから再開」
- 「昨日は休んだ。今日は戻ってきた」
- 「2日空いても、戻れた私、えらい」
このように、自分を責める言葉ではなく、再スタートを許す言葉を準備しておくのです。
これは「習慣化に必要な心理的安全スイッチ」でもあります。
「空白」は継続の一部にしていい
もし、積み木の中に空白のブロックがあってもいいとしたら?
むしろ、その隙間があるからこそ、続いていく道があるのだとしたら?
「やめてしまった」と思ったその瞬間こそ、
再び積み始めるための設計が試されているのです。
小さな成功体験を積み上げる演出
人は、できたという感覚が積み重なると、行動を自然に継続できるようになります。
逆に、「頑張ったのに認められなかった」「変化が感じられなかった」
そうした体験の蓄積は、やる気を静かに削いでいきます。
だからこそ、「積み木式継続法」では成功の演出を意識的に設計することが大切です。
「できた自分」に光を当てる
たとえば、
- チェックリストをつけて、完了の可視化をする
- 小さなログを残して、自分の言葉で振り返る
- SNSやメモ帳で「今日やったこと」を1行だけ記録する
こうした行動はすべて、「自分は続けられている」という実感の可視化です。
この見える化された手応えが、次の行動を支えるエネルギーになります。
いわば、やる気の燃料を自分で補給していく仕組みとも言えます。
積み木に「名前」をつけよう
毎日の行動にラベルをつけるのも効果的です。
たとえば──
- 「朝のリセット儀式」
- 「未来への1ピース」
- 「静かな革命のはじまり」
こんなふうに、自分だけの物語を添えることで、行動に意味と温度が宿るのです。
積み木は、ただ積むだけではなく、どんな塔を建てたいかという感性と結びつけることで、
習慣は単なるルーティンから、あなたらしい成長の象徴へと変わっていきます。
継続を記録で可視化しよう(ログの力)
継続において、「やったかどうか」を自分の中だけで判断していると、感覚があいまいになりがちです。
昨日はやった気がする。でも一昨日は?
あれ、もう3日空いてる?…となった瞬間、やる気は霧のように消えていきます。
そんな時に必要なのが、記録というアンカー(錨)です。
ログは「自分の時間」を見える化する
ノートでもアプリでも付箋でも構いません。
「続いている軌跡」を目に見える形に残すことが、習慣継続を支える大きな柱になります。
たとえば──
- カレンダーに〇をつける
- スマホのメモ帳に日付だけ記録する
- 習慣アプリで通知つきログを残す
- 紙のノートで習慣一覧を自作する
こうしてログを残すと、「自分は少しずつでも進んでいる」という客観的な安心感が生まれます。
その感覚が、次の1日を乗り越えるエネルギーになるのです。
記録=自分との小さな会話
記録には、単なる数値以上の価値があります。
それは、「昨日の自分と今日の自分をつなぐ対話」だからです。
「今日はここまでできた」
「昨日はサボった。でも、今日は戻ってきた」
そうしたやりとりを重ねることで、あなたの中にもう一人の応援者が育っていきます。
小さな積み重ねを見えるようにすること。
それこそが、「積み木式継続」の推進力であり、自分に優しくなれる仕組みづくりでもあります。
続けられる人の背景にはしくみがある
「この人は意志が強いな」「あの人は続ける力があるな」
そんなふうに思える人を見たことはありませんか?
でも実際は、意志の強さだけで習慣を続けている人はほとんどいません。
彼らが続けられる理由は、その背景に「しくみ」があるからです。
習慣はしくみで支える時代へ
たとえば、
- 毎朝同じ時間にカフェへ行き、そこで勉強する
- 机の上に「やることだけ」を置き、他は見えなくする
- スマホを別室に置き、物理的に触れないようにする
- タスク管理アプリで、今日だけ見る設定にする
これらはすべて、「やるべきことを自然に選べる環境」を作る工夫です。
やらない理由を減らすことが、継続を支える最強の戦略になります。
意志ではなく「構造」に頼る
「今日は気分が乗らない」
「もう少し休みたい」
そんな日があってもいいのです。
でも、そんな時こそ、積み木のようなしくみが支えてくれる。
行動の入口を軽くする
成功を演出する
空白を許容する
記録を残す
再開できる構文を持つ
これらの仕組みを整えていくことで、
人は特別な人にならなくても、続けられる人になれるのです。
結びに
積み木式継続法は、「続けなきゃ」と肩に力を入れるのではなく、
続いてしまう形を自分で設計していくための思考法です。
毎日ひとつ、指先で積んでいくように。
完璧でなくてもいい、小さくてもいい。
気がつけば、あなたの前には「できた」という名の塔が立っているはずです。