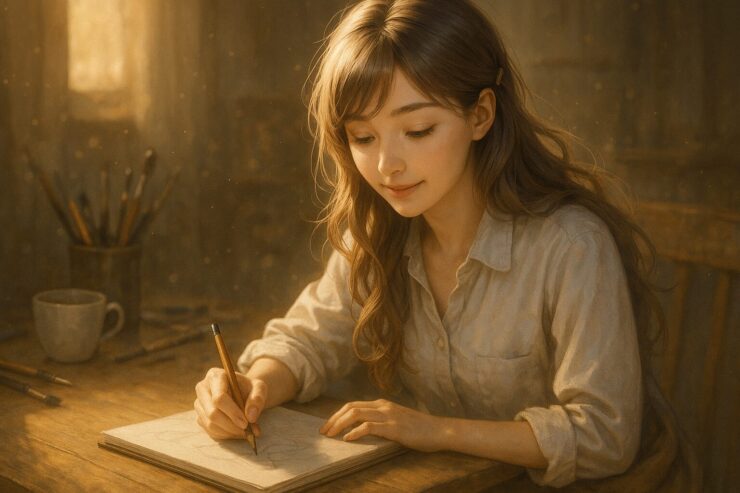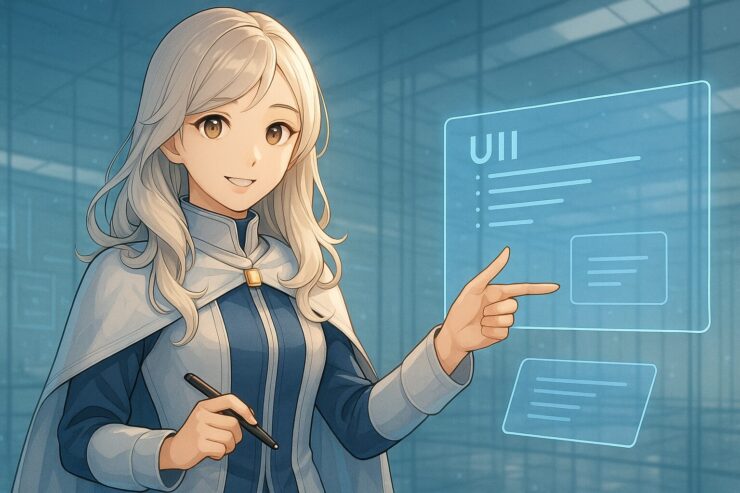目次
Affinityが「無料」になった日、何が起きたのか
それは、長く続いた有料と独占の時代に、静かな変化を告げる一報でした。
2025年10月、プロ仕様デザインツール「Affinity」が完全無料化を発表。
かつてAdobe製品の買い切り代替として人気を集めていたこのシリーズが、突如としてすべてのユーザーに開放されたのです。
開発元のSerif社は、2024年にCanvaの傘下へ入り、以降1年をかけて製品群を統合。
その結果、Affinity Designer(Illustrator相当)/Photo(Photoshop相当)/Publisher(InDesign相当)が、1本のアプリとしてシームレスに扱える環境になりました。
そして今回の無料化によって、プロユースの設計思想がそのまま「初心者でも手の届く」世界にまで広がったのです。
この動きは、単なる価格改定ではありません。
誰もが創造できるというCanvaの理念を、ローカルアプリのレベルまで拡張する戦略にほかなりません。
クラウド中心のCanvaと、オフライン完結のAffinity。
両者を結ぶことで、ネット環境やOSを問わず、誰もが編集を始められるデザインの民主化が加速しました。
とくに注目すべきは、サブスク疲れを抱えたクリエイター層への開放感です。
これまでAdobe Creative Cloud(CC)の高額サブスクリプションに頼らざるを得なかった層に、「無料でもここまでできる」という希望を示しました。
SNSでは「もうPhotoshopを開かなくていい日が来た」「CanvaとAffinityで十分」という声が広がり、ツールの重心が大きく動き始めています。
しかし、この変化は同時に、業界全体に問いを突きつけています。
プロフェッショナルの価値とは、ツールの価格で決まるものなのか。
あるいは、創る意思そのものがプロを定義するのか。
無料化とは、コストを下げるための施策ではなく、創造の入口を誰にでも開くための合図。
その扉が開かれた瞬間、ツールの競争は「値段」から「体験」へとシフトしました。
そしてそれこそが、Canva×Affinityが放つ最大のメッセージなのです。
Canva×Affinity連合とは何か?プラットフォームの逆襲
かつて「誰でも簡単に」を体現する存在だったCanva。
そのCanvaが今、プロの領域をも飲み込もうとしている…
Affinityの完全無料化は、その最初の一手でした。
CanvaがAffinityの開発元Serif社を買収したのは2024年。
WebベースのデザインツールであるCanvaと、ローカルアプリであるAffinityは、当初は異なる文脈に属していました。
しかし今、両者は「あらゆる創作スタイルを受け止めるデザインプラットフォーム」として統合されつつあります。
Canvaが得意とするのは、スピードと簡潔さ。
テンプレートを選び、画像と文字を入れ替えれば、すぐにSNS用のバナーやサムネイルが完成します。
一方のAffinityは、レイヤー・ベクター・色補正などの編集自由度が極めて高く、一から設計する工程に強い。
両者が手を取り合ったことで、「すぐに作れる」×「深く仕上げられる」というデザイン導線が成立しました。
たとえば、Canvaで作ったラフ案をAffinityで微調整し、最終出力へ。
あるいはAffinityで構成された紙媒体デザインを、CanvaにインポートしてSNS展開用に再構成する。
このような双方向の編集フローが、既にユーザーの間で自然に使われ始めています。
さらにCanva側では、AIによる生成系機能も充実しています。
「Magic Write」でキャプションや文章を自動生成、「Magic Media」で動画や画像をプロンプトから生成可能。
Affinity単体にはAI生成こそ搭載されていませんが、Canvaとの接続によって、AI機能を外部から取り込める設計が整いつつあります。
この連合が意味するのは、単なるツールの足し算ではありません。
それは、「誰でも作れる」時代から「誰でも、プロのように作れる」時代への転換です。
そしてこの流れが示唆するのは、今後ますます「ツールは一つではなく、組み合わせるものへと進化する」ということ。
Canva×Affinity連合が持つのは、機能だけではありません。
ユーザーの創りたいに寄り添う構造そのものなのです。
対抗軸としてのAdobe:Fireflyとサブスクの現在地
画像編集といえば、Photoshop。
デザインといえば、Illustrator。
映像なら、Premiere Pro──
この3つの名を知らぬ者はいないほど、Adobeはクリエイティブの中枢を築いてきました。
しかしその王国にも、いま転機が訪れています。
それが、「AI時代への対応」と「高額サブスクリプションの限界」です。
まず、Adobeが提示する次世代の鍵は「Firefly」
これは同社が独自に開発した生成AIモデル群であり、画像生成・動画編集・音声合成・ベクター生成などを網羅します。
たとえば、Photoshopでは「生成塗りつぶし(Generative Fill)」で背景をAIが補完、Premiere ProではAIが不要フレームを補い、Acrobatでは文章の要約や契約比較もAIが行う…
作業を任せるという概念が、現実になりつつあるのです。
さらにAdobeは、AIをただのツールではなく、ワークフローを統合する頭脳として育て始めています。
Firefly Boards(プロジェクト単位で生成結果を整理)や、エージェントAI(Product Support/Data Insights など)を導入し、デザイナーだけでなく、マーケターやビジネス部門まで巻き込んだAI活用基盤を築こうとしています。
その一方で、問題もあります。
それは「高額な使用料と制限された生成枠」という、利用者にとっての二重の壁です。
Adobe製品の多くはサブスクリプション制。
Photoshop単体で月額3000円前後、Creative Cloudコンプリートプランでは年間9万円以上という価格帯も珍しくありません。
しかもFireflyによる生成機能の一部はクレジット制となっており、「月に何回まで生成可能」といった制限が設けられています。
この構造は、頻繁に使うプロには合理的でも、ライトユーザーには過剰な投資に見えることもあります。
実際、SNS上でも「Fireflyに魅力はあるが、元が取れる気がしない」「課金の境界が見えにくい」といった声があがっています。
では、それでもなぜ多くのプロはAdobeを使い続けるのか。
その答えは明白です。「業界標準」であり、「連携力」が圧倒的だからです。
Adobeの強みは、ツール群が一つのクラウド基盤で連動している点にあります。
Photoshopで作ったデザインを、そのままIllustratorで編集し、Premiereで動画化し、Adobe Fontsでフォントを補い、Adobe Stockから素材を取得し、Acrobatで納品する。
この連鎖こそが、Adobeを総合芸術インフラに押し上げている所以です。
ただし、ここで忘れてはならないのは、業界標準は永遠ではないということ。
かつての王者であっても、選ばれ続けなければその座は揺らぎます。
そして今、その挑戦者としてCanvaとAffinityが現れました。
価格、使いやすさ、AI、自由度、
何を重視するかによって、ツール選びの地図が大きく塗り替えられようとしているのです。
これから始めるならAffinity:無料でもここまでできる


「画像編集は難しいもの」
そう思っていた人にとって、
Affinityの無料化はまるで扉が開いたような体験になるかもしれません。
Photoshopのような複雑なUIも、Canvaのようなテンプレート依存でもない。
Affinityはその中間、プロの機能を、素人でも使える文法で届けてくれるアプリです。
まず特筆すべきは、3つのモードが統合されていること。
- Affinity Designer:ベクター編集(ロゴ、イラスト、図解など)
- Affinity Photo:写真補正・レタッチ・レイヤー合成
- Affinity Publisher:ページレイアウト、冊子・PDF編集
これらが、ワンクリックで切り替え可能なスタジオ一体型で搭載されています。
つまり、1つのファイル内で「イラストを描き、写真を合成し、ページを組む」という編集の流れがシームレスに行えるのです。
そしてこの「プロ級の3機能」がすべて無料。
これほどの恩恵が、個人クリエイターや副業・ブログ・note運営者にとって、どれだけ大きな意味を持つか。
たとえば、
- noteのカバー画像を自分の手で構成できる
- ブログで使うアイキャッチや図版をテンプレに頼らず制作できる
- Kindle出版用の表紙・本文レイアウトもAffinity一つで完結できる
しかも、出力形式(PNG/JPG/PDF/SVG/PSDなど)も豊富で、WordPressとの相性も良好。
SNS投稿、電子書籍、印刷物、あらゆるアウトプットに耐えうる柔軟性があります。
では、初心者には難しいのでは?
そう感じる方もいるかもしれませんが、AffinityはUIが非常に洗練されています。
Photoshopよりも直感的で、タブレット的な操作性が随所にある。
複雑な設定よりも、「この形をどう動かしたいか?」という視点で動けるインターフェースになっているのです。
また、公式チュートリアルもYouTubeや公式サイトで充実。
コミュニティも広がっており、「無料だから放置される」という印象とは真逆の育っているツールという印象が強まっています。
Affinityは、テンプレートに頼らない自分で組む楽しさを教えてくれます。
そして何より…
「あ、私にもできた」という、小さな成功体験を重ねてくれるツールです。
それが、これから画像編集を始める人にとって、何よりの財産になるのです。
Canvaがあるなら、なぜAffinityが必要なのか?
「Canvaがあれば、もう十分じゃない?」
画像編集を始めたばかりの人から、そんな声を聞くことがあります。
実際、Canvaは素晴らしいツールです。
直感的な操作、豊富なテンプレート、美しいフォント、AIによるデザイン提案……
誰でもそれなりに整ったものを作れるという点では、群を抜いて優秀です。
しかし、その「整った世界」が、時に創造の壁になることもあるのです。
Canvaの根底にあるのは、テンプレートベースのデザイン。
つまり「枠に当てはめる」ことが前提です。
もちろん、それで十分な場面も多くあります。
ですが、次第にこう感じる瞬間が訪れるのです。
「この構図、前にも見たな……」
「フォントや余白、もっと自分らしく調整したい」
「もうちょっと自分で考えて組みたいのに」
ここにこそ、Affinityの必要性があります。
Affinityは、テンプレートがありません。
かわりにあるのは、まっさらなキャンバスと構造をつくる道具です。
図形を組み、レイヤーを重ね、パスを調整し、色を定義する。
これらの作業は、言い換えれば「思考の構造化」そのもの。
見た目を飾るのではなく、自分の中の情報や感情を図解として表現するプロセスがAffinityにはあります。
また、CanvaとAffinityは相反する存在ではありません。
- Canvaで構成したSNS用テンプレをAffinityで仕上げる
- Affinityで組んだ書籍やnote用の図版を、Canvaにインポートしてマルチ展開する
といった片翼ずつの編集ではなく、両翼で飛ぶワークフローが可能です。
Canvaは、速さと外見の整えに優れる。
Affinityは、構成と仕組みの設計に強い。
この2つを持つことは、「早く作れる力」と「深く創れる力」の両方を持つことに他なりません。
テンプレートの中で閉じるか。
テンプレートの外へ、自分で広げていくか。
Affinityは、その次の問いに応えてくれる道具なのです。
Adobeへ進化する人と残る人を分ける2つの鍵
Affinityで始め、Canvaで慣れた人が、次に考えるのは
「Adobeに移行すべきか?」という問いです。
この問いに、正解はありません。
しかし確かなのは、移るか否かを左右する鍵は、たった2つの軸に集約されているということです。
①:「AI機能を戦力として使うか?」
いま、AdobeはジェネレーティブAI企業へと姿を変えつつあります。
- Photoshopでは、生成塗りつぶし(Generative Fill)で背景やオブジェクトをAIが補完
- Illustratorでは、プロンプトからベクター生成が可能に
- Premiere Proでは、AIが音声と映像を自動同期・ノイズ除去
- Acrobatでは、契約文書を要約・比較・ハイライト
- さらに最近では動画・音声・アバターまでもAIで生成できる時代へ。
これらのAIは、単なる補助を超えています。
クリエイティブの中心にAIを据え、全体の流れを最適化するのがAdobeの狙いです。
もしあなたが、「制作量を10倍にしたい」「動画編集や音声処理を自動化したい」と考えているなら、
その時、Adobeが提供するAIは進化の道として有効な選択肢となるでしょう。
一方で、「自分のペースで手を動かしながら作るのが好き」「構成や表現の設計こそが価値だ」と感じるなら、
AffinityやCanvaの自由度と軽快さのほうが、感性に寄り添ってくれる場面も多いはずです。
②:「コストは投資と捉えられるか?」
Adobe最大のハードルは「サブスクリプションモデル」と「生成クレジット制」です。
- 単体プラン(月額3000円前後)
- コンプリートプラン(年額7〜9万円以上)
- FireflyやAI機能は生成数に上限あり(クレジット制)
- 将来の料金改定やプラン変更も想定される
このような環境に対して、「それでも使う価値がある」と思えるかどうか。
プロにとっては「仕事道具としての必要経費」ですが、
個人クリエイターや副業レベルの方にとっては、回収可能な成果が見込めるか否かが分岐点となります。
- 継続的に案件を受けている
- チームで素材を共有している
- 法人案件や納品物が多い
といった条件があるなら、Adobeへの移行は戦略的判断として妥当です。
しかし、
- 趣味で表現をしたい
- マイペースで創作を楽しみたい
- ライフスタイルに無理なくツールを取り入れたい
という人にとっては、無料〜中価格帯のCanva・Affinityのほうが、余白のある創作環境となるでしょう。
分かれ道は「AIに任せるか、自分で紡ぐか」
Adobeが目指すのは、効率化された創造の頂点です。
その恩恵を享受できる人には、間違いなく強力な味方となるでしょう。
けれど、構図を組み、色を選び、言葉と視線の流れを設計していく──
そんな「創るという行為そのもの」にこだわりたい人にとっては、
Adobeは先の選択肢として温めておく存在で良いのかもしれません。
いまはまだ、AffinityやCanvaという柔らかなフィールドで、
思考と感覚を耕していく段階。
そしてその先に、必要ならば選べるという余裕があることが、
なにより大きな価値なのです。
画像編集のはじめかた:3ステップで選ぶ自分のツール
画像編集に興味がある、
けれど、ツールが多すぎてどれから手をつければいいのかわからない。
Canva?Affinity?Adobe?どれが正解なの?
そんな風に立ち止まってしまう人へ、ひとつの考え方を贈ります。
ツール選びに迷ったら、「目的 → 機能 → コスト」の3ステップで決めてみてください。
これは、どんな場面にも応用できる「自分に合ったツール選びの構文」です。
STEP 1:自分が何を作りたいかを言語化する
- SNS用のアイキャッチ?
- noteのカバーや図解?
- ブログ記事用の装飾画像?
- Kindleの表紙やレイアウト?
- プレゼン資料やLPの構造図?
- デジタルZINEや印刷物?
作りたいものが明確になると、ツールに求める力も見えてきます。
たとえば「SNS用の見栄えを整えたい」ならCanvaが最適。
「一から図を設計したい」ならAffinity。
「商用の映像制作や3D合成まで想定している」ならAdobeが必要かもしれません。
STEP 2:必要な機能がどこまであるかを比べる
チェックポイント例:
| 機能 | Canva | Affinity | Adobe |
|---|---|---|---|
| テキスト入力・装飾 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 写真補正・明るさ調整 | △ | ◎ | ◎ |
| レイヤー編集 | △ | ◎ | ◎ |
| ベクター編集 | △ | ◎ | ◎ |
| AI画像生成 | ◎(Magic) | × | ◎(Firefly) |
| PDF・印刷対応 | ◯ | ◎ | ◎ |
| UIの直感性 | ◎ | ◯ | △(慣れが必要) |
| 学習コスト | 低 | 中 | 高 |
ポイントは、「あれもこれも」ではなく「自分に必要なところだけ」比べること。
全部が最強のツールなど存在しません。
大切なのは、自分の今のサイズに合った機能を持っているかどうかです。
STEP 3:コストを負担ではなく未来への投資として考える
- 無料で始めたい → Canva/Affinity(どちらも◎)
- 数ヶ月だけ必要 → Canva Pro(月額1500円前後)
- 本格的に仕事で使う → Adobe Creative Cloud(年額7万円〜)
ここで注意すべきは、「高いから良い」「無料だからダメ」という発想に縛られないこと。
Affinityは無料でもプロ級。
Adobeは高いけれど業界連携が強い。
Canvaは無料でも爆速で使える。
どれも「正しい」──でも、「あなたに合う」は別です。
最終判断は「いまの自分を肯定できる選び方かどうか」
ツールは、上手になるための手段であって、完成された自分の象徴ではありません。
だからこそ、こう考えてみてください。
- Canvaで始めることは、「スピード」を選ぶこと。
- Affinityで学ぶことは、「構造思考」を選ぶこと。
- Adobeに移行することは、「武装して未来に進む」こと。
どれを選んでも、あなたの価値は揺らぎません。
でも、選んだあとに「これでよかった」と言える準備は、選び方に宿るのです。
だから迷っても、大丈夫。
この3ステップが、あなたにぴったりの編集ツールへ導いてくれるはずです。
結論:まずはAffinity、未来はAIとともに
はじめて何かを作るとき、
必要なのは、たったひとつの「できた」の実感です。
それは、難しい機能でも、高価なサブスクでもなく、
手の中にあるツールが、いまの自分にちょうどよいことから始まります。
今回、Affinityが無料になったことで、画像編集の世界は大きく変わりました。
構図を組む。色を整える。余白を設計する。ページを並べる。
それらすべてが買い切りも課金もなしで手に入る時代が、とうとう来たのです。
そしてその背景には、Canvaという巨大なビジュアルプラットフォームがあり、
そのさらに向こうには、Adobeというプロの道具箱が存在し続けています。
無料ではじめて、AIとともに進化する。
この流れは、創作だけでなく働き方や発信スタイルさえも変えていくはずです。
今この瞬間からできること。
未来のために選ぶこと。
そのどちらにも「答え」はあります。
だからこそ、はじめの一歩にAffinityを。
より速く、より広く表現したくなったらCanvaを。
そして、より深く、より精度を求める日が来たらAdobeへ。
選択肢が増えたこの時代に大切なのは、
いつでも進める未来を、自分のポケットに持っておくこと。
画像編集の旅は、始めるだけでいいのです。
すべては、その一歩から始まります。